透過型電子顕微鏡法(Transmission Electron Microscopy:TEM)は電子顕微鏡法の一種で、サンプルに高エネルギーの電子ビームを照射し、透過した電子ビームの強度分布を検出することで微細構造を観察する方法です。わずかな形状や密度の違いにより、電子ビームの透過状況や散乱状況が変化し、それにより微細構造が可視化されます。
手順と構造
TEM法の典型的な手順は次のようになります。
- 1. 試料作成: 薄い膜状になるように試料を作成します。光学顕微鏡と違い、電子ビームは試料を貫通しきる能力が低いため、薄い試料が必要です。
- 2. 電子照射: 高エネルギーの電子ビームを試料に照射します。
- 3. 観察: 透過した電子ビームの強度分布を検出し、微細構造を観察します。
また、TEMは以下のような構成になっています。
- 電子銃: 高エネルギーの電子ビームを発生させる部分です。
- 照射装置: 電子を試料に照射する部分です。
- 試料ステージ: 試料を配置する部分です。
- 像検出器: 電子ビームの強度分布を検出する部分です。
特徴
TEMは、分解能が非常に高いことが特徴です。
原子レベルの観察が可能で、構造生物学や材料科学などで利用されます。
また、電磁レンズを利用するため光学的な歪みが少なく、高精度な情報が得られます。
しかし、試料の準備が難しく、結晶構造など特定の条件を満たす試料のみ適用可能です。
具体例
たとえば、タンパク質の微細な立体構造を観察する際にTEMが利用されます。
高エネルギーの電子ビームを利用することで原子レベルまで精密に観察することが可能です。
立体構造を決定する他の手法
X線結晶解析法や核磁気共鳴法は、タンパク質の立体構造を解析する他の手法です。
X線結晶解析法は、X線の回折を利用して結晶状態のタンパク質の立体構造を観察する方法です。
核磁気共鳴法は、磁場の中で原子核の磁気モーメントが共鳴する性質を利用して物質の構造や動きを観察する方法です。
これらの手法と比較して、TEMは試料の物理的な状態(薄切り状)を直接観察する点で異なります。また分解能の高さも特徴的です。
一方で、試料が透明な薄片である必要があり、試料作成が困難です。
最近では、クライオ電子顕微鏡法という新手法も開発されています。これは試料を急速冷凍させることで試料の状態を保持し、そのままの形で観察する方法で、生物学的な観察に特化しています。
歴史と経緯
電子顕微鏡は1931年にマックス・クノールとエルンスト・ルスカによって最初に開発されました。
その後、さまざまな改良が加えられ、現在の高分解能なTEMが開発されています。
問題点と対応策
TEMの主な問題点は、試料の準備が難しい点と、試料自体にダメージを与えてしまう可能性がある点です。
これらの問題に対する対応策として、低温での観察(クライオ-TEM)や、電子ビームのエネルギーを低減するなどの技術が開発されています。
応用
TEMは生物学や材料科学だけでなく、さまざまな分野で応用されています。
例えば、半導体の製造過程で微細な構造の確認や、新素材の微細構造の観察などに利用されます。
また、生物学ではウイルスや微生物の構造解析にも利用されています。これらの情報は、新薬の開発や病原体の研究に役立てられています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

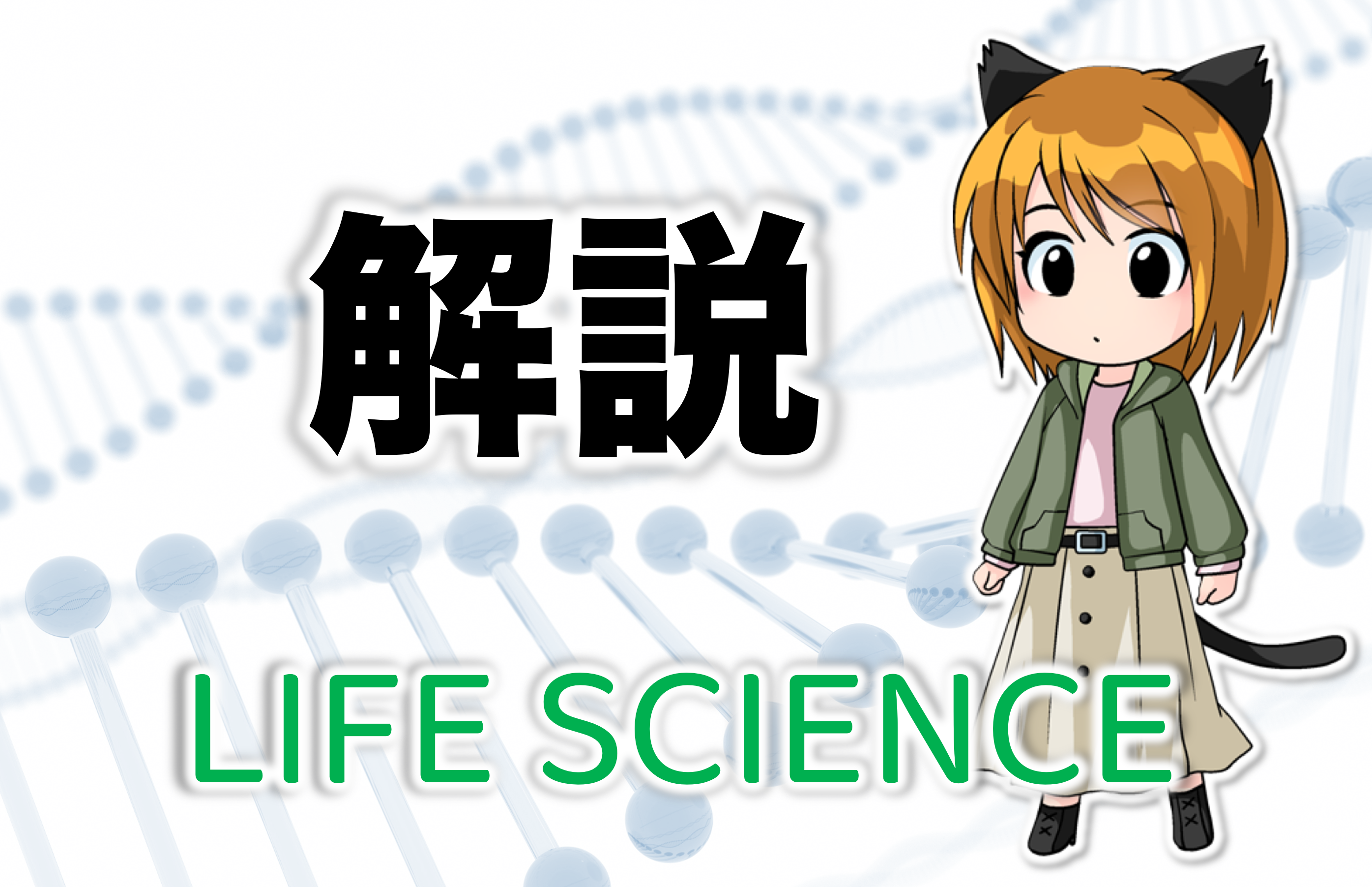

コメント