プロテオームとは、ある時刻における細胞や組織に存在する各タンパク質の量のことを指します。
意義
細胞の状態はゲノムだけでは決まりません。機能する実体であるタンパク量が細胞の状態や機能を決定します。そのため、全てのタンパク質の量であるプロテオームの測定が重要です。
プロテオームは細胞の状態や環境等によって変動する、非常に複雑で動的な情報です。このプロテオームの特徴を理解することで、生命現象の整理、解析、理解ができ、また、各種疾患の診断や治療に対する新たなビジョンや知見を得ることが可能になります。
実験および解析手順
具体的なプロテオーム解析手順は以下のような流れで行われます。
- 1. サンプルの準備 : 解析対象の生物、細胞、組織から抽出対象のタンパク質を抽出します。
- 2. タンパク質の分解 : 抽出したタンパク質を特定の酵素(例:トリプシン)にてペプチド断片に分解します。
- 3. ペプチドの分離と検出 : ペプチドを特性に応じて分離し、その質量や電荷などを検出します(質量分析が一般的)。
質量分析では、ペプチドの質量と電荷の比から、そのペプチドのアミノ酸配列の推定と自動的にタンパク質にマッチングすることができます。また、2D-PAGE(二次元ポリアクリルアミドゲル電気泳動)による解析も広く行われており、タンパク質の分子量と電荷から2次元のパターンを生成し、特定のタンパク質の増減などを視覚的に把握することができます。
課題と対応策
プロテオームの解析は、技術的な難しさや高いコストなどが課題となっています。また、その複雑さと動的な性質から、プロテオーム全体を一度に解析することは非常に難しいとされています。各タンパク質の量的変動や構造変化を網羅することは現在の技術では難しいです。また、細胞外のタンパク質や細胞膜タンパク質の解析はさらに困難です。
これらの課題への対応策として、特定のタンパク質群に焦点を絞ったターゲテッドプロテオミクスの手法が開発されています。これにより、特定の生物学的な問いに対してより深い洞察を可能にすることが期待されています。また、質量分析技術の進歩やAIの導入もプロテオーム解析の新たな可能性をもたらしています。
とはいえ、これらの対応策もまだ十分な解決策にはなっていません。プロテオームの全体像を理解し、それを生物学や医学に役立てるためには、さらなる技術開発と理論構築が求められています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

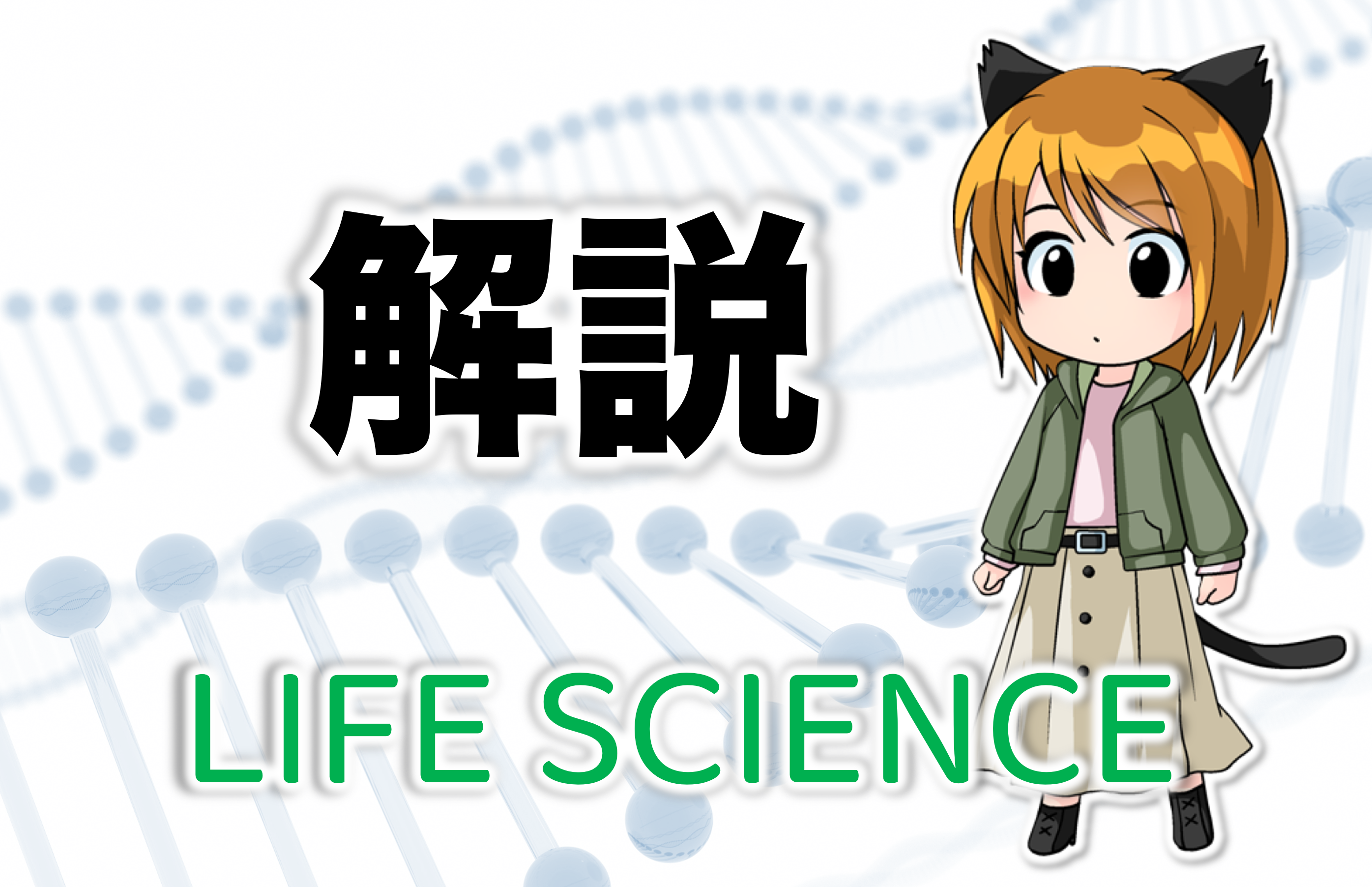

コメント