ナノポアは直径が数ナノメートル(nm)の穴を利用したシーケンス技術(Nanopore Sequencing)です。これはDNA or RNAの配列を決定する方法の一つで、Oxford Nanopore Technologies社が開発した技術です。
原理
DNAシーケンシングのためのナノポアは、脂質二重層または固体基板上に形成されます。ナノポアに電圧をかけるとイオンがポアを通過し電流が流れますが、この時DNA分子がポアに差し込まれると電流が一時的に減少します。DNAの各塩基は特有の電流ブロックパターンを示し、このパターンを元にDNAの配列を読み取ります。
手順
ナノポアシーケンシングでは、まずDNAをナノポアに送り込むための酵素を結合させます。次に、電圧をかけることでDNAを引き込みます。DNAがポアを通過する過程で塩基ごとに異なる電流の変化が生じ、これを測定することでDNA配列を決定します。
例えば、電流の変化が順に「0.126, 0.135, 0.144, 0.132 nA」と測定された場合、これを塩基の電流ブロックパターンと一致させて「A, G, C, T」と読み取ります。大量のDNAを順番に通過させることで長い配列を読み取ることができます。
メカニズムと構造
ナノポアは脂質二重層や半導体材料に形成される微小な穴であり、DNAがポアを通過することを物理的に可能にしています。その構造としては、一般的に膜上に1つのポアが存在し、その大きさはシーケンシングに使用される分子の大きさ(DNAなら約2nm)に合わせて作成されます。
DNA分子をナノポアに送り込むためにはヘリカーゼ等の酵素が使用されます。これらはDNAの二重鎖を分離し、一方の鎖をナノポアに進行させることでシーケンシングを可能にします。
特徴と具体例
ナノポアシーケンシングは、ロングリード(長い塩基配列)が直接読み取れる利点があり、これにより次世代シーケンサ等のショートリードによる配列決定では困難であった反復配列等に対する有効性が向上します。また、リアルタイムでのシーケンシングが可能なため、現場での迅速な診断や研究が可能です。
具体的な例としては、Oxford Nanopore Technologiesの「MinION」や「PromethION」があります。これらは小型で手軽にDNAシーケンシングを行えるため、実験室からフィールドまで幅広い環境で使用されています。
関連する概念や用語との比較
次世代シーケンサ(NGS)とは、大量のDNAを並列に高速でシーケンシングする技術全般を指します。NGSにはイルミナ社の方式やロッシュ社の454方式、Ion Torrentの方式などがあります。これらは読み取り対象とする塩基をフローセル上に固定化し、塩基の増幅や合成反応を利用して配列を読み取るため、短いリード(~600bp)しか得られないという特徴があります。
これに対して、ナノポアやPacBioのSMRT(Single Molecule Real-Time)シーケンシングはロングリードを得られる技術です。これは配列組み立てを容易にするための有利点となります。ただしロングリードにはエラーレートが高いという特徴があるため、短いリードを用いて精度を高める必要性があります。
歴史や経緯
ナノポアの歴史は比較的新しく、2005年にOxford Nanopore Technologiesが創業しました。同社はDNAを直接シーケンシングする技術の開発を目指し、2014年にMinIONをリリースしました。同製品は小型で安価にシーケンシングを行え、またリアルタイムでデータを取得できることから大きな注目を浴びました。
問題点と対応策
ナノポアシーケンシングはロングリードを扱うため配列組み立ての容易さを提供しますが、反面エラーレートが高いという課題があります。これは、同じ塩基でも微妙に異なる電流の変化を引き起こし、それが誤読を生む原因となります。
これに対する対策としては、高精度な短いリード(Short Read)を併用することでエラーを訂正することが一般的です。また、AIの進歩により、これら微妙な電流の変化を学習し、より高精度な読み取りを実現する試みも進められています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

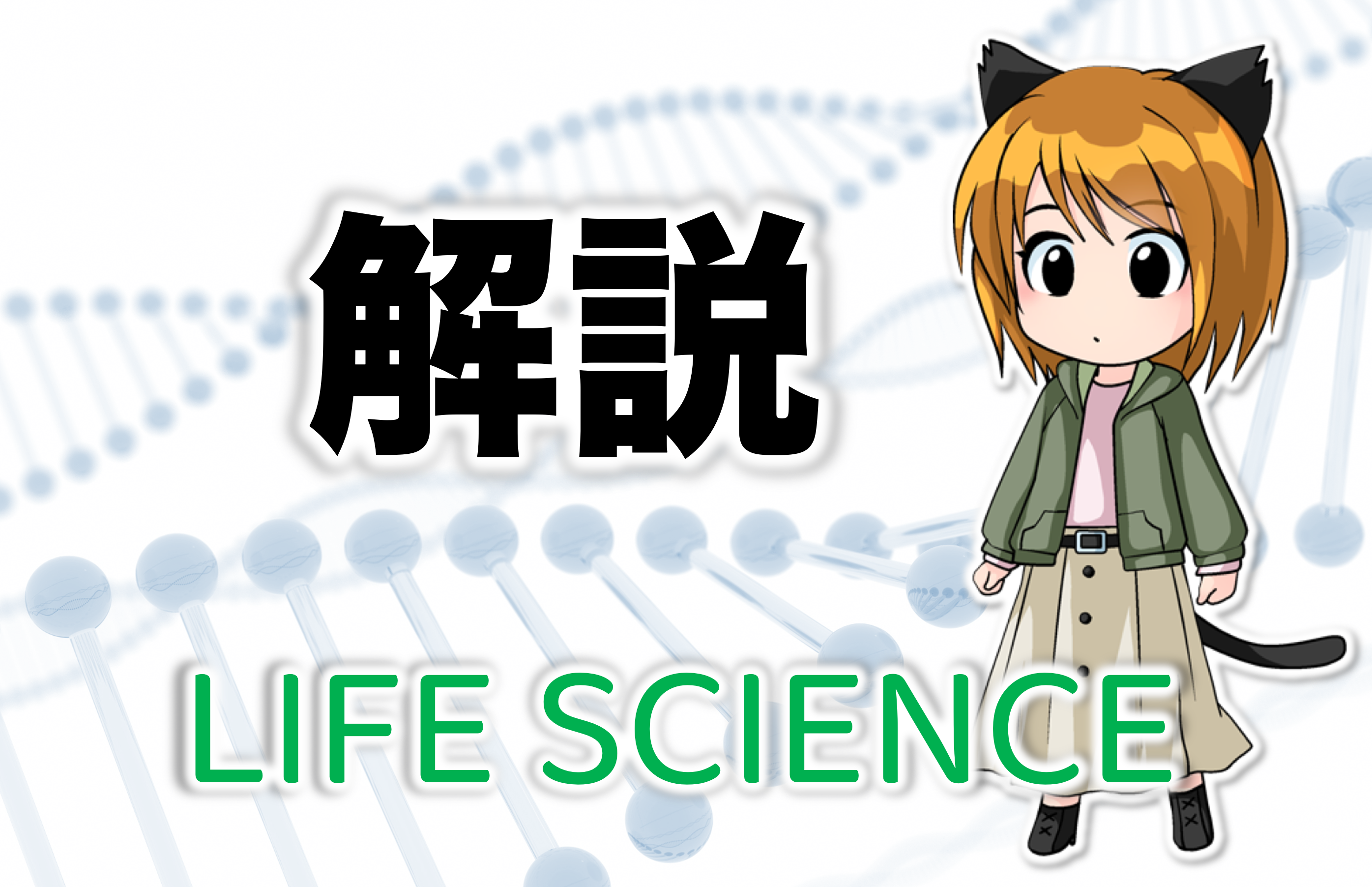

コメント