サンガー法とは、英国の生物学者フレデリック・サンガーが開発した、DNAの配列を決定するための手法の一つです。この手法は、1977年に初めて発表され、その後、ゲノム研究などの分野で広く用いられるようになりました。サンガー法は、忠実性、再現性、そして高いスループット(一度に処理できるサンプル数)の特性を兼ね備えています。サンガー自身はこの業績により1980年のノーベル化学賞を受賞しました。
原理
サンガー法では、A、T、G、Cのうち3つについてはdNTPを、残り1つについてはddNTP(dideoxynucleotide triphosphate)を用いてDNAの合成を行います。塩基は4種類あるため、ddNTPに割り当てる塩基のパターンも4つあり、従ってDNA合成の反応系は4つ行うことになります。
ddNTPは通常のデオキシリボ核酸三リン酸(dNTP)とは違い、3末端にヒドロキシル基がありません。3末端のヒドロキシル基は次のヌクレオチドが結合する場所であるため、ddNTPが組み込まれるとそこでDNA鎖の延長が停止し、ddNTPに割り当てた塩基の位置に対応した異なる長さのDNAが合成されます。
そこで、4つの反応系の合成産物を隣り合うレーンのウェルに配置して電気泳動により分離することで、各レーンに対応する塩基に対応したバンドが現れます。このバンドの位置は配列決定をしたいDNA鎖中における塩基の位置に対応しているため、電気泳動後のバンドの位置を順に追っていくことでDNAの配列が分かります。
手順
サンガー法は以下の手順で行われます
- 1. PCR(Polymerase Chain Reaction)によって目的のDNA断片を増幅します。
- 2. PCRで増幅したDNA断片にDNA primer(開始点)を結合させます。
- 3. DNAポリメラーゼを加えてDNA合成を開始します。一方で、通常のdNTPと一部のddNTPも混ぜておきます。
- 4. DNA合成が進むとランダムにddNTPが組み込まれ、そこでDNA鎖の延長が止まります。これにより、様々な長さのDNA断片が作られます。
- 5. ゲル電気泳動によってDNA断片を分離します。分離の結果、DNA断片の長さ(位置)とddNTPの種類によって色分けされたバンドが現れてDNAの配列を読み取ることができます。
問題点とその対策
サンガー法はその確実性や再現性から広く用いられていますが、いくつかの問題点や課題があります。例えば、その一つは一度の実験で決定できるDNA配列の長さが限られてしまうことです。サンガー法は基本的に約600~900塩基対までの配列しか解読することができません。
また、サンガー法は相対的に時間とコストがかかるという課題もあります。これは大規模なゲノム解析を行う際には大きな問題となります。これらの課題への対策として、次世代シークエンサー(NGS: Next Generation Sequencer)が開発されており、複数のDNA断片を同時に高速にシークエンシングすることができます。ただし、NGSも高価な機器とランニングコストがかかるため、サンガー法が用いられる場面は多いです。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

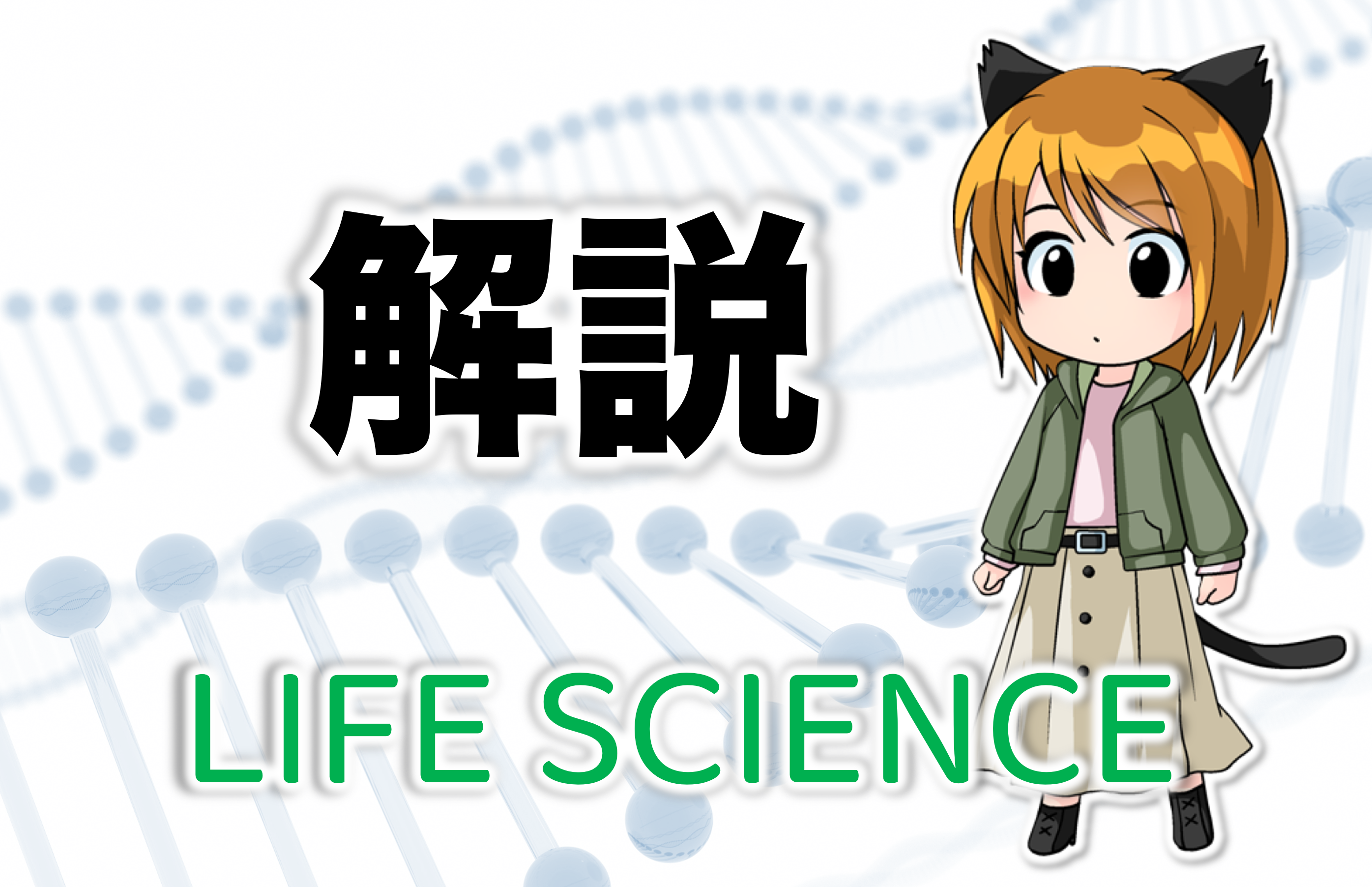

コメント