PCR(Polymerase Chain Reaction)は、特定のDNA断片を大量に増幅する技術です。その手法が画期的で、また様々な研究や診断に応用できるため、生命科学の研究においては、重要な実験方法の一つとなっています。
原理
PCRの原理は基本的にDNAの複製過程を模倣したものです。DNAを構成するヌクレオチドは、A-T、C-Gとペアを作る性質があり、この性質を利用します。基本の流れは次の三段階です。
- 1. 熱変性:鋳型DNAおよび増幅したDNA断片を高温にすることで二本鎖を解離させる
- 2. アニーリング:温度を下げることで、鋳型DNAおよび増幅したDNA断片の特定の部位に相補的な鎖となるプライマー(短いDNA)が結合する
- 3. エクステンション:DNAポリメラーゼと呼ばれる酵素が、プライマーからDNAを延長する
これが1サイクルで、このサイクルを何度も繰り返すことで、目的とするDNA断片だけを大量に増幅させます。
手順
具体的なPCRの手順は以下の通りです。
- 1. 温度を94℃程度まで上げる(熱変性)
- 2. 温度を50-60℃程度まで下げる。このステップの温度はTm値(melting temperature, 融解温度)と呼ばれる。Tm値はプライマーとテンプレートDNAまたは増幅したDNA断片とが安定にhybridize(ハイブリダイズ:結合する、またはアニーリングするともいう)する温度を指します。Tmの計算には、全塩基数やGC含有率などが影響します。
- 3. 温度を72℃程度まで上げる(エクステンション)
- 4. この1-3のサイクルを30-40回繰り返す
フィデリティと増幅効率
用いたDNAポリメラーゼによって、反応のフィデリティ(精度)や効率が変わります。
フィデリティは、エクステンションにおけるDNA合成時にエラーが生じない確率を指します。一般的にTaqポリメラーゼよりも高フィデリティな酵素を使うと、エラーレートが減るため、正確な結果が得られます。
但し、エクステンションにおけるDNA合成の時間が長くなることが多いという欠点があることに注意します。
特徴および応用例
PCRの一番の特徴は、少量のDNAからでも特定の領域を大量に増幅できることです。そのため、体液などから得られたごく少量のDNAでも診断などに利用することができます。
また、PCRは比較的短時間で結果を得ることが可能で、結果の解析も容易であるため、現場での迅速な判定などにも利用されます。
PCRは、遺伝子の研究や、感染症の診断、組織の同定、遺伝子組換えなど、幅広い分野で利用されています。最近では新型コロナウィルスの検査にも使われており、その有用性が再認識されています。
歴史と経緯
PCRの原理を提唱したのはアメリカの生物化学者ケイリー・バリックスで、1983年に発表しました。その後、何度も改善が加えられ、現在ではさまざまなバリエーションが開発されています。PCRの開発により、分子生物学の研究は飛躍的に進展し、1993年にはケイリー・バリックスにノーベル化学賞が授与されました。
問題点と課題およびその対策
PCRで取り上げられる課題としては、エラーレートの問題や、増幅効率の問題があります。
エラーレートについては、高フィデリティな酵素を使うことで対策を取れます、目的に応じた選択が必要です。
増幅効率については、実験条件(プライマー設計、アニーリング温度など)の最適化により改善が図られます。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

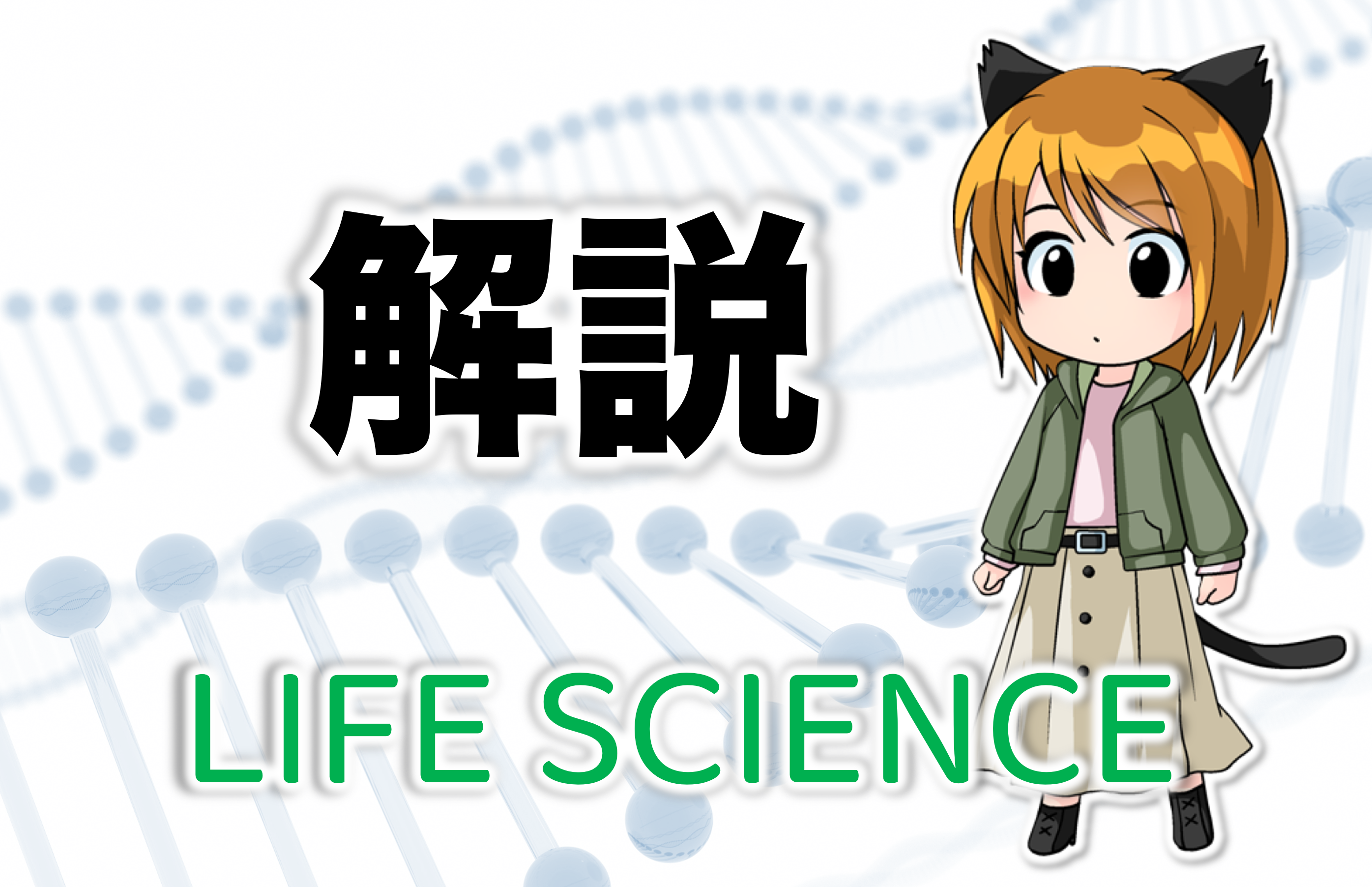

コメント