次世代シーケンサ(Next Generation Sequencer:NGS)は、一度に大量のDNA配列を決定することができる高出力型のDNA配列決定装置です。これにより、ゲノム全体の塩基配列を短期間で決定すること等が可能となりました。
原理
ライブラリの準備
次世代シーケンサはDNA断片を直接読むことはできません。そこで、次世代シーケンサが配列決定できるようにDNA断片を編集します。具体的にはDNA断片を数百塩基程度にまで更に断片化し、アダプターと呼ばれる配列を両端に付加をして、PCRで増幅します。
次世代シーケンサの配列決定の機序では、あまりに長いDNA断片をシーケンスすることはできないため数百塩基程度への断片化が必要です。また、次世代シーケンサではDNAポリメラーゼによる相補鎖合成により配列を決定しますが、その際のプライマーが結合する場所を提供するためにアダプターの付加が必要です。
以上のプロセスを経て、次世代シーケンサが配列決定できるように変換したものをライブラリーと呼びます。
クラスタ生成
次世代シーケンサーの一種であるIlluminaの方式では、フローセルと呼ばれるアダプターに相補的なDNA断片が結合したガラススライドに、ライブラリーのDNA断片を結びつけます。
このガラススライド上でブリッジアンプリフィケーションと呼ばれるPCRの一種が行われ、DNA断片が結合した周辺に同じ配列のDNA断片が作成されます。このように周辺に同じDNA断片を作成した状態をクラスタと呼びます。
次世代シーケンサではクラスタに対してDNAポリメラーゼが相補鎖を合成する際に放射される蛍光を認識して配列を決定しますが、クラスタを形成しない場合、蛍光強度が弱すぎて検出できません。そのため、クラスタ形成というステップが必要になります。
Sequence by Synthesis
次世代シーケンサの配列決定の基本的な原理はSequence by Synthesis(SBS)です。SBSでは、配列決定をしたい各DNA断片についてDNAポリメラーゼが相補鎖を合成すると同時に塩基配列も決定します。
具体的には、DNAの各配列(A、G、C、T)を識別するために異なる蛍光タグが付いたdNTPを用意し、シーケンスしたいDNA断片に対してDNAポリメラーゼがdNTPを取り込む際に蛍光が放射されるようにします。この発光パターンを観察することにより、DNA配列を決定します。
リード
「リード(Read)」とは、次世代シーケンサによって配列決定された配列のことを指します。より具体的には、次世代シーケンサの出力形式であるFASTQ形式内に記載されているDNA配列のことです。
次世代シーケンサでは、数百塩基に至るDNA断片について、その片側または両端の配列を、一度に数百万から数十億本シーケンスします。
なお、イルミナの次世代シーケンサが出力する配列(リード)の長さは75塩基または150塩基であることが多く、ショートリード等と呼ばれます。
シングルエンドおよびペアエンド
シングルエンドリードはDNA断片の一方の端をシーケンスします。一方、ペアエンドリードは同じDNA断片の両端をシーケンスします。
次世代シーケンサの具体例
Illumina社の「MiSeq」や「HiSeq X Ten」などがあります。
それぞれ一回のランで読み取ることができるデータ量、読み取り長さなど、具体的なスペックが異なります。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

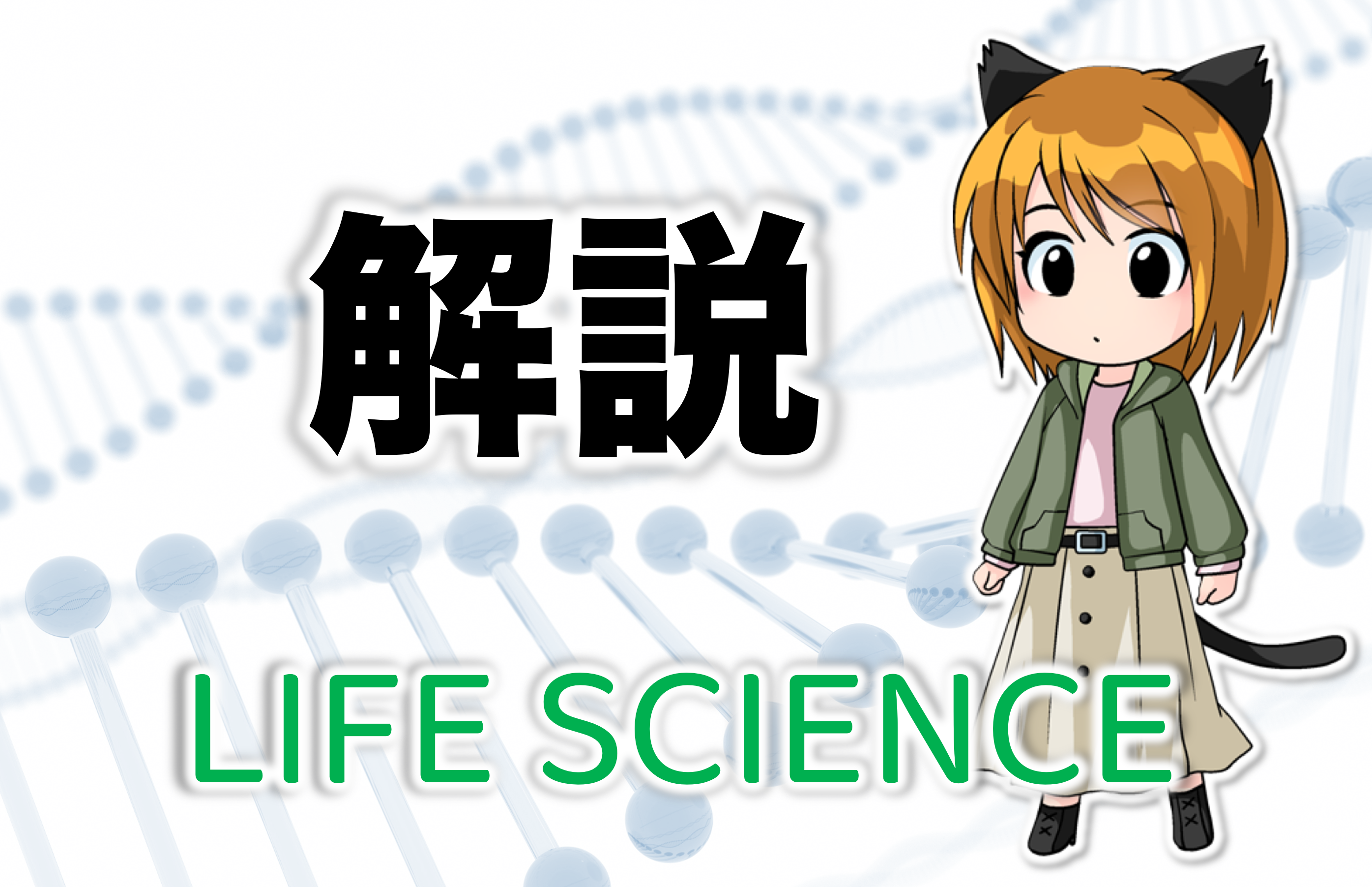

コメント