X線結晶解析法(X-ray crystallography)はX線が物質によって回折する性質を利用し、物質の結晶構造を明らかにする手法です。結晶中の原子配列がX線の回折パターンとして現れ、そのパターンを分析することで結晶格子の3次元構造が解読できます。
原理
ブラッグの法則という式が基本的な原理になります。すなわち、X線が結晶格子の原子層からの反射を受け、その間で生じる干渉を正の干渉とすると、ブラッグの法則は以下のように表されます。
$$
2d\sin\theta = n\lambda
$$
ここで、
- $d$は結晶の基面間の間隔
- $\theta$はX線と結晶面の間の角度
- $n$は整数(通常は$1$)
- $\lambda$はX線の波長
を示します。
結晶中の原子配列がX線の回折パターンを形成し、そのパターンを分析することで結晶格子の3次元構造が解読されます。この原理は干渉と回折という光波の性質に基づいています。
手順
具体的な手順としては、まず対象となる物質を純度の高い単結晶にします。
その上で、この結晶にX線をあて、回折パターンをフィルムや検出器で観測します。
その後、その回折パターン(実際には回折強度のパターン)から物質の結晶構造を推定します。
そのための計算はパターンの回折角(ブラッグ角)から得られる情報を用いて行われ、その詳細は非常に複雑です。
特徴
元々鉱物の結晶構造を解析するために考案された方法ですが、現在ではタンパク質などの巨大分子の構造解析にも使われています。
その最たる例が1950年代にDNAの構造がX線結晶学によって解明されたことです。
また、この方法は非破壊であり、結晶の組成や純度に影響を与えません。これは試料の再利用を可能にすると同時に、連続的な実験や測定に適しています。
歴史・経緯
X線結晶解析法は1912年にマックス・フォン・ラウエによって初めて実験的に証明され、その業績によりラウエは1914年にノーベル物理学賞を受賞しました。
その後、ブラッグ父子による解析手法の確立や、1962年のDNAの構造解明など、この手法は生物学や物質科学の進歩に大きく貢献してきました。
問題点・課題と対応策
X線結晶解析法には試料を単結晶にする必要があることが大きな課題です。特に生物学的な実験では、純度の高い単結晶を作ることが困難であることが多いです。加えて、非晶質や結晶化しにくい物質はこの方法で解析することができません。
これに対する解決策として、結晶化が困難なタンパク質などの構造を解析するための、核磁気共鳴法 (NMR) や電子顕微鏡法があります。これらの方法は結晶化する必要がなく、溶液状態や近自然状態での構造を解析できます。
核磁気共鳴法
核磁気共鳴法(NMR)は分子の構造解析に使われる手法の一つで、電磁波(ラジオ波)を用いて試料の核スピンの状態を測定し、その情報から分子の構造を推定する方法です。
透過型電子顕微鏡法
透過型電子顕微鏡(TEM)は超微細な構造を見るために高エネルギーの電子ビームを試料に照射し、その透過電子を利用して試料の像を作り出す手法です。
クライオ電子顕微鏡法
クライオ電子顕微鏡法(Cryo-EM)は生物学的な試料を超低温下で凍結し、それを電子顕微鏡で観察する方法です。結晶化することなく、ほぼ自然状態の形で分子の3次元構造を観察することができます。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

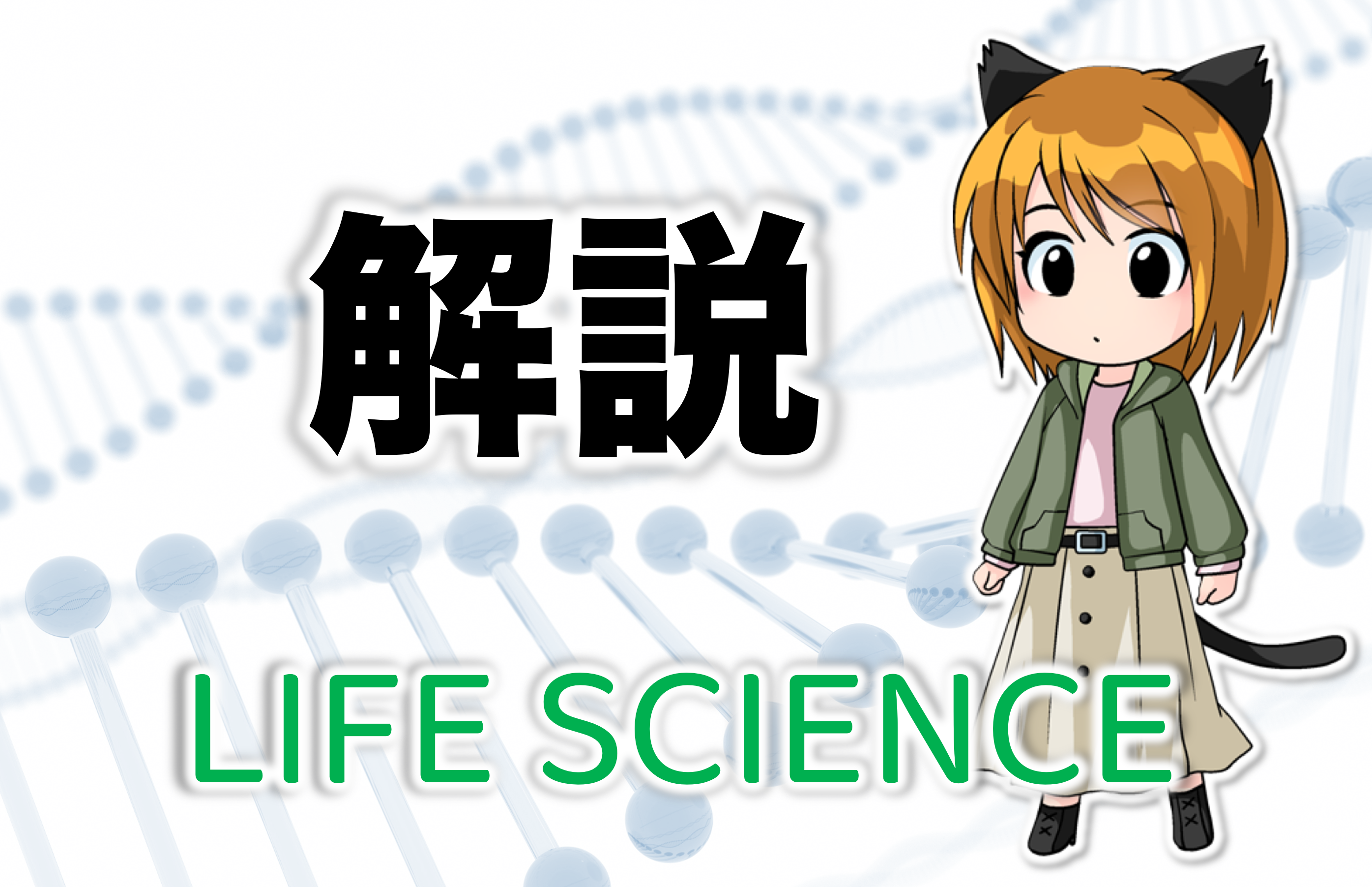

コメント