アンピシリンは、化学式$\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{N}_{3}\text{O}_{4}\text{S}$を持つ半合成型の広義スペクトルペニシリン系抗生物質です。アミノペニシリンの1つであり、グラム陽性菌及びグラム陰性菌に対する抗菌作用を持つ特性を持っています。
作用機序
アンピシリンは、細菌の細胞壁合成を阻害することで作用します。
細菌の細胞壁は、ペプチドグリカンと呼ばれる物質で構成されています。アンピシリンは、このペプチドグリカンの合成を阻害することにより、細菌の増殖と分裂を阻止します。
構造
アンピシリンは、β-ラクタム環と呼ばれる4員環構造を持っています。
このβ-ラクタム環はペニシリン系抗生物質の特徴的な構造で、この構造が細菌の細胞壁合成を阻害する作用を持っています。
β-ラクタム環が持つ官能基が細菌のペプチドグリカン合成酵素と結合し、その活性を阻害することで抗菌作用を発揮します。
抗菌活性の評価
アンピシリンの抗菌活性を評価するための実験には抗生物質敏感度試験(ディスク拡散法)などがあります。その手順は以下の通りです。
- 1. 細菌をシャーレに作成した寒天培地に塗布し、その上にアンピシリン含有のディスクを置く。
- 2. 一定時間(通常24時間)培養した後で、アンピシリンが効果を発揮した領域(細菌が生育出来なかった円状の領域の半径など)を測定する。
特徴
アンピシリンは、ペニシリン系抗生物質の中でも広範囲な細菌に対する抗菌活性を持つため、広義のスペクトラム抗生物質とされます。特に、グラム陰性菌に対する効果があります。
アンピシリンは口から服用することができ、注射薬としても用いられています。そのため、病院だけでなく家庭でも用いられることがあります。
しかし、一部の細菌はβ-ラクタマーゼという酵素を持っており、これによりアンピシリンを分解してしまい抵抗性を持っています。
具体例
アンピシリンは、中耳炎、髄膜炎、細菌性心内膜炎、尿路感染症、胆道感染症など、さまざまな感染症の治療薬として使用されます。
関連する薬剤
アンピシリンはβ-ラクタム抗生物質の一つであり、このグループには他にもペニシリンGやアミノペニシリン、カルボペニェム、モノバクタムなどがあります。
これらの抗生物質の共通の特徴は、β-ラクタム環という酵素を阻害する構造を持っており、これが細菌の細胞壁の形成を阻止することにより抗菌活性を発揮しています。
問題点と対応策
アンピシリンの主な問題点の一つは、耐性菌の出現です。これに対する一つの対応策として、サルバスタチン系の薬剤を併用することがあります。これにより、β-ラクタマーゼの作用を阻害することで抗生物質の効果を持続させることができます。
また、アンピシリンにはアレルギー反応を引き起こす可能性があります。これに対する対策として、初めてアンピシリンを服用する患者には慎重に監視することが重要です。
応用
アンピシリンは、微生物学の研究における培養基の添加物としても利用されています。特に、遺伝子工学においては、プラスミド(遺伝子組換えベクター)の導入に成功した細菌を選択的に増やすための選択マーカーとして使われます。
経緯・歴史
アンピシリンは1961年にイギリスの研究者たちによって開発されました。
これは、初めて開発された半合成ペニシリン系抗生物質であり、それ以前に使用されていたペニシリンよりもはるかに幅広く抗菌作用を持ち、体内で吸収されやすかったと評価されました。
そのため、多くの感染症の治療に使用されるようになり、その重要性は現在も続いています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

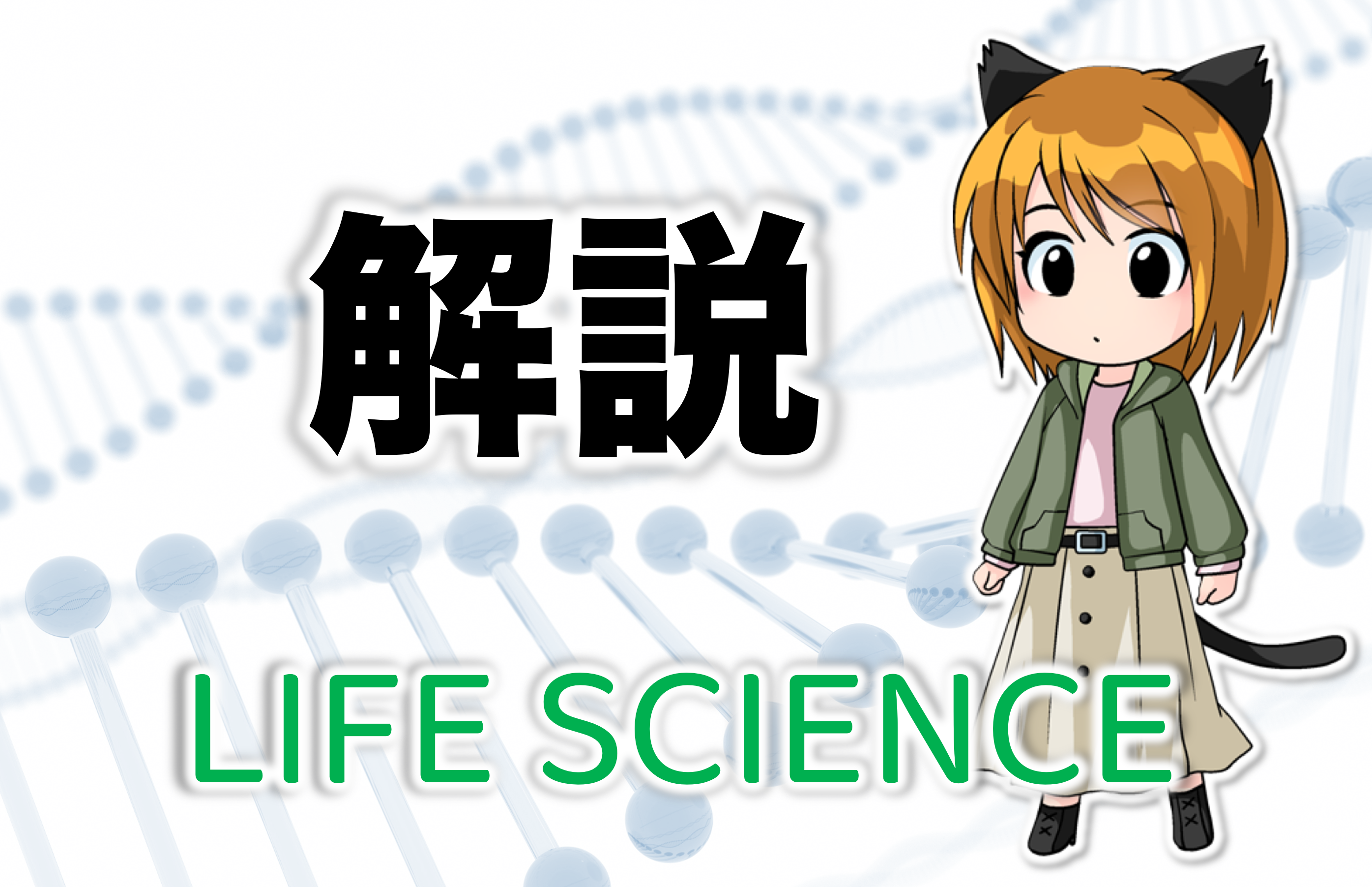

コメント