ZFN(Zinc Finger Nuclease)は、「ジンクフィンガーヌクレアーゼ」という名のゲノム編集技術の一つです。この技術は、遺伝子工学によって進化したものであり、遺伝子の特定の場所を切断したり、配列を挿入できる能力を有しています。
原理と手順
ZFNの原理は、ジンクフィンガードメインと呼ばれるDNA結合ドメインと、フラバノイドスモドキヌクレアーゼと呼ばれるDNA切断ドメインを組み合わせた人工酵素であることが基礎となっています。
ZFNの作成手順は基本的に以下のような流れになります。
- 1. 目的のDNA配列(ターゲット配列)に対するジンクフィンガープロテイン(ZFP)を設計・合成する。
- 2. このZFP遺伝情報をヌクレアーゼ(FokI)と結合させる。
- 3. 結合させたZFNを細胞に取り込ませることで、ターゲット配列を切断する。
この結果、ZFNによって遺伝子が切断され、細胞が自己修復する過程で新たな遺伝情報が組み込まれるか、または切断された部分が効率よく除去されます。
特徴
ZFNの最大の特徴は、他のゲノム編集技術(CRISPR/Cas9、TALEN)と比較して、対象とする遺伝子部位の選択範囲が狭いことです。それはZFNがターゲットとするDNA配列がジンクフィンガープロテインの設計により決定されるためで、一般的に18~24塩基対のDNA配列をターゲットとします。
しかし、この特徴が逆にZFNの利点となる場面もあります。狭い範囲の遺伝子を高精度で操作できるため、特定の遺伝子を効率良く操作する必要がある場合には、ZFNが適しています。また、ジンクフィンガープロテインは、様々な構造や機能を持つ遺伝子に対しても結合することが可能で、多様性に富んでいます。
問題点と課題
ZFNは、精度が高く、特定の遺伝子を効率良く操作できるという利点がありますが、一方でいくつかの問題点や課題を抱えています。
まず、ZFNの開発コストが高いという問題点があります。ZFNを開発するためには、ターゲット配列に対するジンクフィンガープロテインを設計・合成する必要がありますが、これらの設計・合成は複雑で、コストもかかります。
また、操作精度が高い一方で、ターゲット配列の範囲が狭いため、対象とする遺伝子部位の選択範囲が限られるという課題があります。
これらの問題点と課題を解決するためには、新しいZFNの開発方法の研究や開発技術の進化が求められます。
歴史と経緯
ZFNの技術は、1996年に初めて発表されました。酵素FokIのDNA切断活性を有する部位と、DNA結合能を持つジンクフィンガープロテインを組み合わせることで、特定のDNA配列を認識・切断することが可能な人工酵素を開発しました。それ以降、ZFNはその効率と精度の高さから、ゲノム編集の強力なツールとして用いられています。
しかし、その後登場したCRISPR/Cas9やTALENといったゲノム編集技術が、簡便さと広範囲な遺伝子操作能力から注目され、現在ではこれらの技術が主流となっています。それでも、特定の遺伝子を高精度に操作したいというニーズから、ZFNも引き続き研究・応用されています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

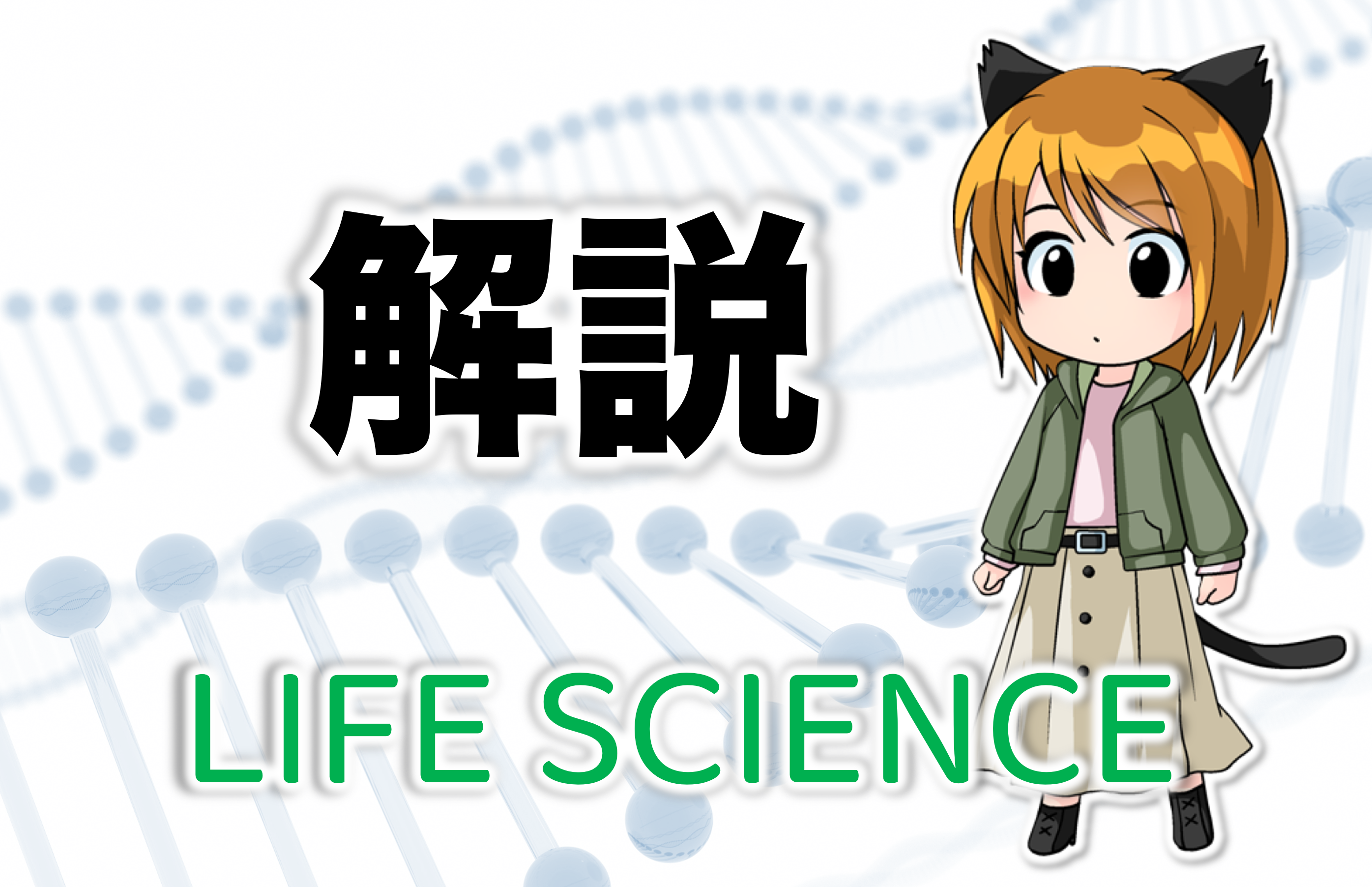

コメント