CRISPR/Cas9(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR associated protein 9)は、細菌や古細菌がウイルスから身を守るための免疫システムであるCRISPR系の一部を利用した、ゲノム編集技術のことを指します。
原理
CRISPR/Cas9システムは、RNA分子とCas9という酵素から構成されます。RNA分子(sgRNA)は、特定のDNA領域を認識するために必要な配列(crRNA)と、Cas9酵素に結合するための配列(tracrRNA)から成ります。
RNA分子は、対象のDNA領域に結合し、Cas9酵素を該当部分へ誘導します。Cas9酵素は、RNA-DNA複合体の形成と活性化を経て、対象のDNA領域で2本鎖の切断を行います。
2本鎖の切断が生じた後、その修復過程におけるエラーを利用し、該当領域に対してノックアウトやノックインを実現します。
手順
ゲノム編集を行うには、まずsgRNA(crRNAとtracrRNAの融合体)を作ります。次に、このsgRNAとCas9タンパク質を細胞内に導入します。sgRNAは目標となるDNAシーケンスに結合し、Cas9はその部位を切断します。細胞はDNAが切断されると、その壊れた部分を修復しますが、その過程でDNAシーケンスに変更を加える事ができます。
DNAの修復は主に二つの方法、つまり、非相同末端結合(NHEJ)と相同組換え(HR)により行われます。NHEJはDNA断末を直接繋ぎ合わせるため、結果として数ヌクレオチドの挿入や欠失が引き起こされます。一方で、HRは、相同配列を持つDNA分子をテンプレートにして精密に欠損部を修復します。
他のゲノム編集技術との比較
他のゲノム編集技術に比べ、CRISPR/Cas9はより簡単で効率的です。
ZFNやTALENはいずれも専用に設計したタンパク質が必要で、開発に時間と費用がかかります。
一方、CRISPR/Cas9はRNAガイドによってターゲット領域を決定するため、使いやすさとコストの面で優れています。
歴史や経緯
CRISPR/Cas9システムは、当初細菌(化膿レンサ球菌)の防御システムとして発見されました。
細菌がウイルスに感染すると、そのゲノムを認識して核酸を切断し、ウイルスの増殖を防ぎます。この現象はCRISPRと名付けられました。
問題点や課題とその対応策
CRISPR/Cas9によるゲノム編集は、オフターゲット効果(非特異的なゲノム領域が切断される現象)といった問題があります。
新たなCasタンパク質の開発やガイドRNA設計の最適化により、問題解決が進められています。
応用
現在、CRISPR/Cas9は、医療(遺伝病の治療、がん治療)、農業(作物改良、病害虫防除)、生物学(生物の進化、生物環境の理解)など、さまざまな分野で応用が進められています。将来的には、さらに多岐にわたる分野での活用が期待されています。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

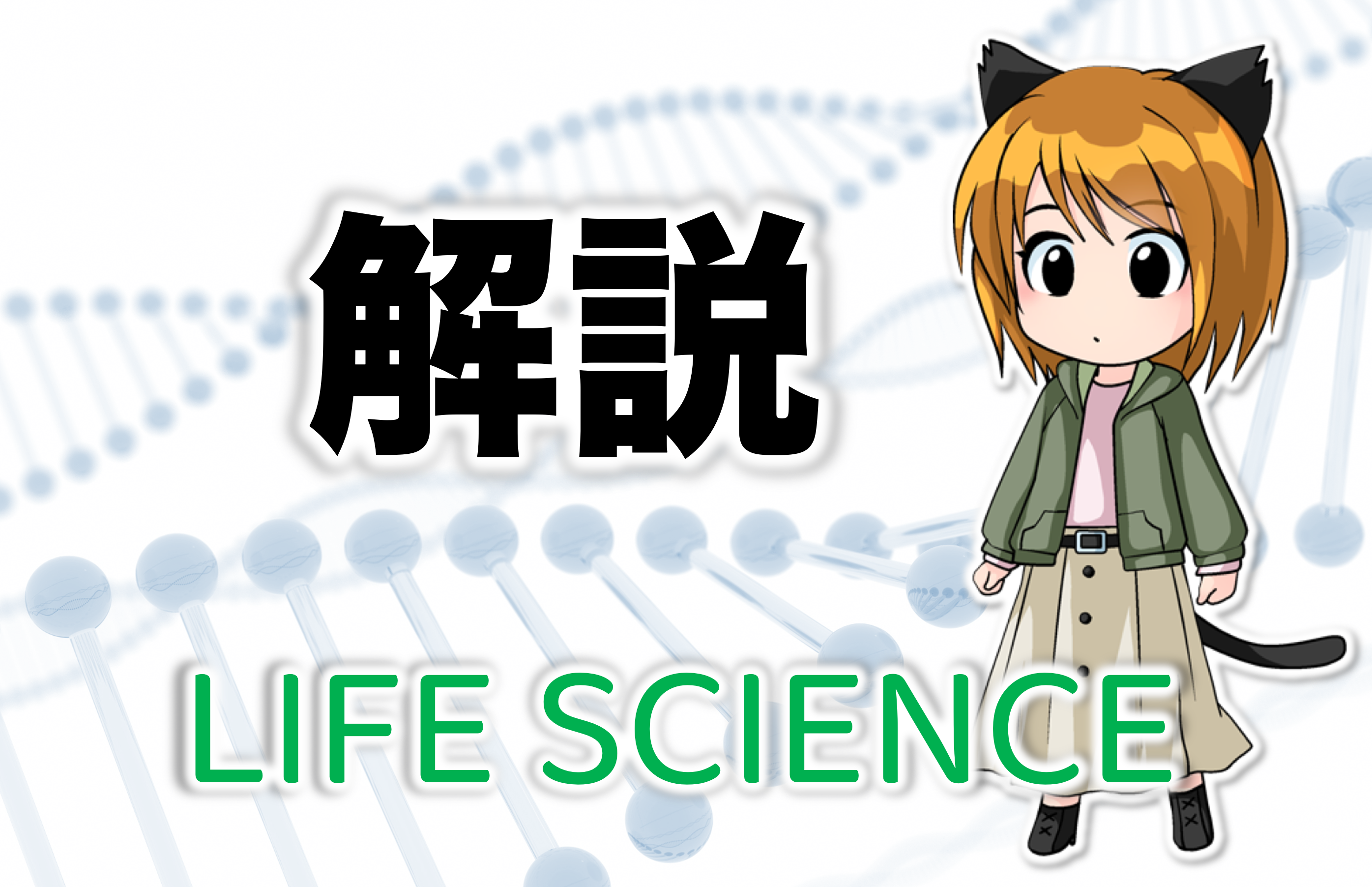

コメント