人工染色体とは自然界に存在する染色体をベースとしたベクターで、ホストの染色体からは独立して安定に次世代に受け継がれ、数百万塩基対の長さのDNAも組込み可能なツールです。
種類
人工染色体には、対象とする宿主によって、ヒト人工染色体(Human Artificial Chromosome: HAC)、酵母人工染色体(Yeast Artificial Chromosome: YAC)、細菌人工染色体(Bacterial Artificial Chromosome: BAC)などの種類があります。
構造と機序
染色体はDNAとタンパク質からなる構造体であり、両端にテロメアと呼ばれる構造と、染色体分裂時に必要なセントロメアという構造を持っています。
人工染色体では、これらの構造体と解析したい遺伝子を組み合わせて新たに染色体を作り出します。
こうして得られた人工染色体は、細胞中で自力で複製し、それが細胞分裂とともに娘細胞に伝わります。
実験手順
人工染色体の作成は以下の手順で行われます。
- 1. まず、導入したい遺伝子や遺伝子群をPCRなどで増幅します。
- 2. 増幅した遺伝子を人工染色体に導入して組み込みます。ベクターとして使用する染色体は、既存の染色体に遺伝子を組み込むための接着部位を持っています。
- 3. 宿主細胞に人工染色体を導入します。この際、ベクターはナノ粒子やリポソームなどで包まれて宿主細胞に送り込まれます。
- 4. 宿主細胞はベクターを取り込み、その中の人工染色体が細胞内で倍増します。その結果、導入した遺伝子が宿主細胞内で機能を果たすようになります。
なお、以上の手順以外にも、トランスポゾンやゲノム編集技術を用いることで、より精緻な人工染色体の作成・解析が可能です。
人工染色体の問題点とその対応策
人工染色体の作成は比較的容易ではありますが、その後の維持や解析が困難であるという問題があります。
この問題を解決するための対応策としては、例えば、人工染色体のサイズを小さくする技術や、宿主本来の染色体DNAにコードされている遺伝子発現に影響を与えずに遺伝子を導入する技術などが研究開発されています。
プラスミドとコスミドベクター
プラスミドとは、細菌などの細胞内に存在する小さな円形のDNAで、遺伝子を組み込むためのベクターとして広く利用されています。プラスミドベクターは遺伝子のクローニングに用いられ、所望の遺伝子を導入するための組み換えが容易であるためによく利用されます。ただし、クローニング可能なDNA断片の長さは長くても5kb程度になります。
一方、コスミドベクターとは、プラスミドとウイルスの性質を併せ持つベクターであり、プラスミドよりも長い遺伝子を導入できる利点があります。最大で約55kb程のサイズのDNA断片をクローニング出来ます。ただし、コスミドベクターの扱いはプラスミドベクターほど簡易ではないため、大規模な遺伝子クローニングに用いられます。
これらのベクターに対し、人工染色体は更に長いDNA断片をクローニングすることができます。具体的には数百万塩基対の長さのDNA断片をクローニングすることが可能です。
人工染色体の応用
人工染色体は、遺伝子治療や個々の遺伝子に対する機能解析などの分野で活用されています。
遺伝子治療では、患者の体内に導入し、遺伝病の原因となる遺伝子の正常版を体内で作動させることにより、遺伝病の治療に利用されます。
また、個々の遺伝子に対する機能解析では、特定遺伝子の働きを調べるために使われます。通常、一つの遺伝子の機能解析を行うには、該当遺伝子が欠けているモデル生物が必要になりますが、人工染色体を使用すれば、特定の遺伝子の機能のみを独立して評価することが可能です。
参考書籍
バイオ実験基本セット
- これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド (KS生命科学専門書)
- イラストでみる超基本バイオ実験ノート―ぜひ覚えておきたい分子生物学実験の準備と基本操作 (無敵のバイオテクニカルシリーズ)
- 改訂 バイオ試薬調製ポケットマニュアル〜欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント
- バイオ実験法&必須データポケットマニュアル―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ
- バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない
バイオ実験イラストレイテッド
- バイオ実験イラストレイテッド〈1〉分子生物学実験の基礎 (細胞工学別冊 目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド②
- バイオ実験イラストレイテッド〈3+〉本当にふえるPCR (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド④
- バイオ実験イラストレイテッド〈5〉タンパクなんてこわくない (目で見る実験ノートシリーズ)
- バイオ実験イラストレイテッド⑥
- バイオ実験イラストレイテッド⑦

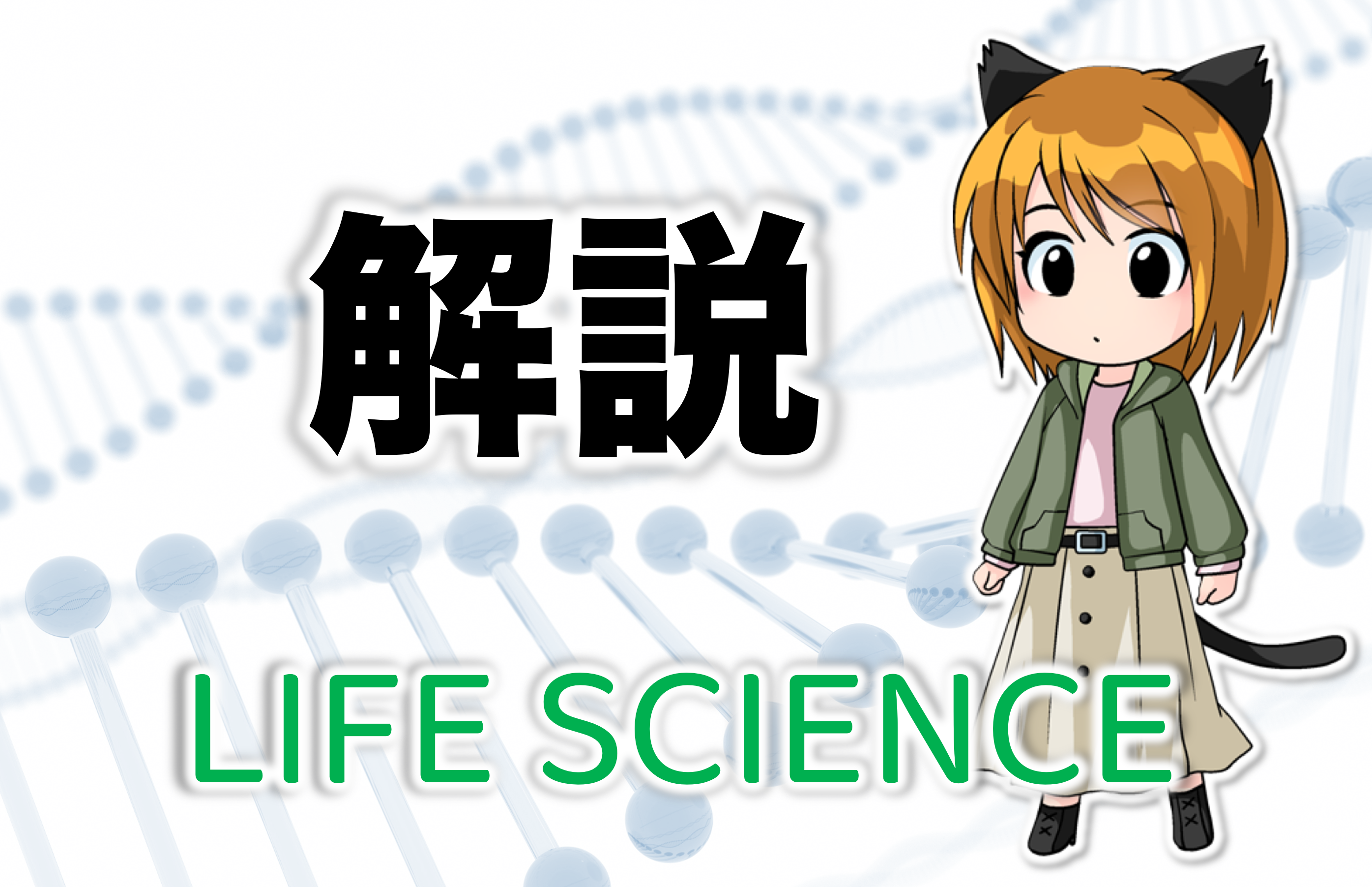

コメント